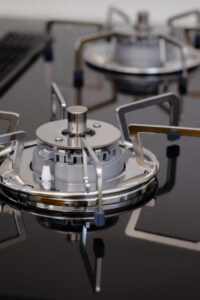参照元:大津町|定額減税に伴う不足額給付金について
大津町は、国の経済対策として令和6年度に実施された定額減税に伴い、物価高騰の影響を受けた生活者を支援するため、「定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下、不足額給付金)を支給します。これは、令和6年分の所得税額や定額減税の実績額が確定した後、当初の定額減税補足給付金(調整給付)の金額を本来給付すべき額が上回った人に対して、その不足額を支給するものです。
支給対象者
不足額給付には、主に二つの対象者がいます。
- 不足額給付(1)の対象者 令和7年1月1日時点で大津町に在住、または大津町から令和7年度住民税を課税されている人のうち、当初調整給付金の算定と令和6年分の所得税および定額減税の実績額との間に不足が生じる人が対象です。ただし、1万円単位の切り上げ額に不足が生じない場合や、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外です。 具体的には、令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少した人や、子どもの出生等で扶養親族が増加した人、税額修正により令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人などが給付対象となりうるとしています。
- 不足額給付(2)の対象者 個別の書類提示(申請)により給付要件を確認する必要がある人で、以下のいずれの要件も満たす人が対象です。
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること。
- 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること。
- 低所得者向け給付金(令和5年度非課税世帯向け7万円、令和5年度均等割のみ課税世帯向け10万円、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯向け10万円)の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと。 具体的には、青色事業専従者や事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円を超える人などが給付対象となりうる例として挙げられています。
参照元をご確認ください。