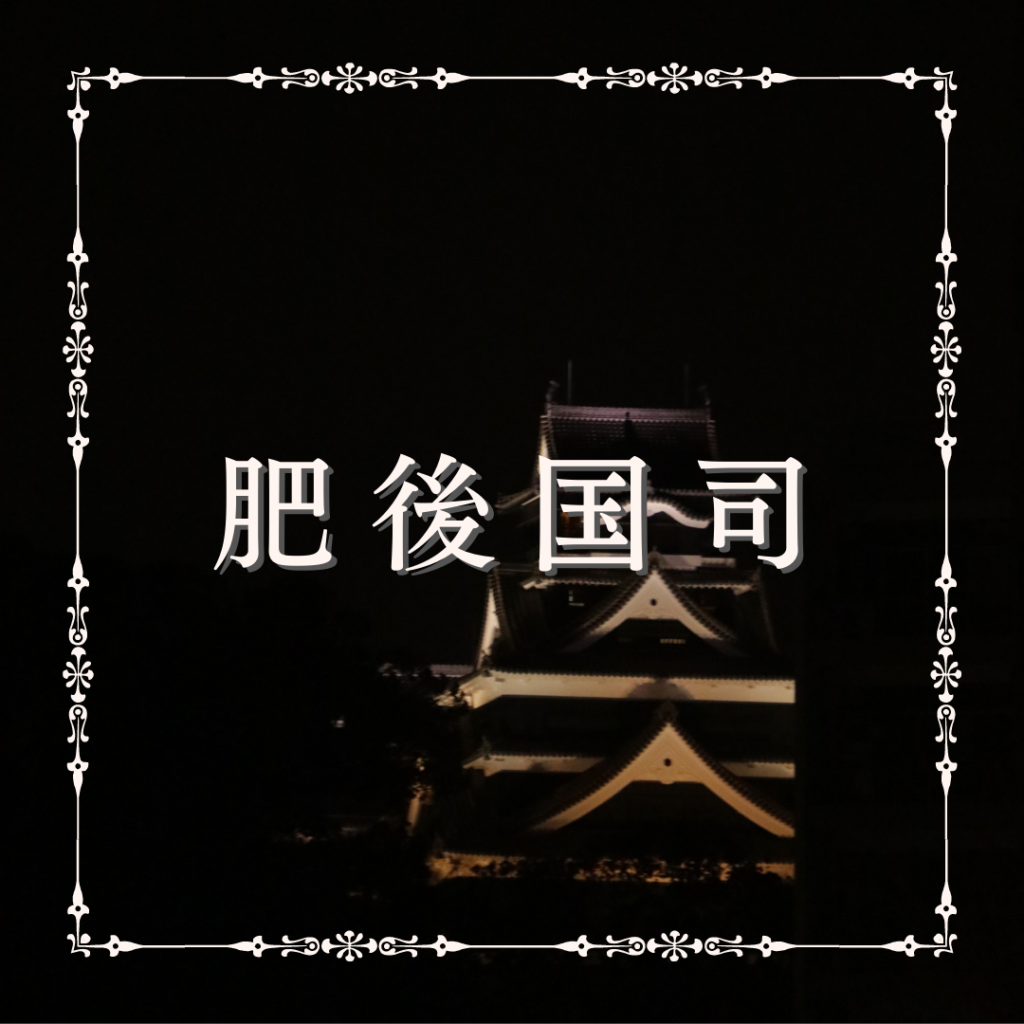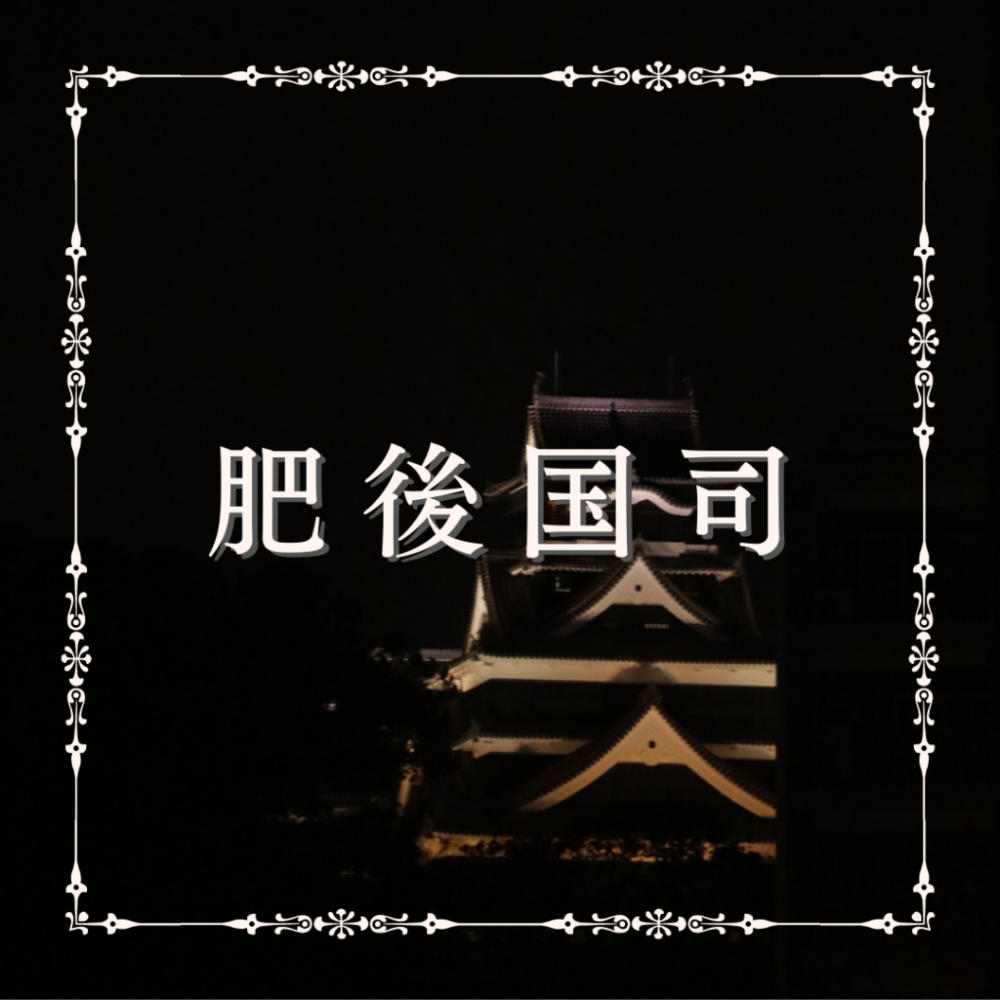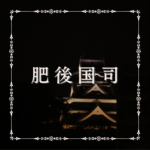古来より 肥後国 を任されし者たち
「肥後国」が「火の国/肥の国」から分かれた時期はいつだろうか。火の国は景行天皇の熊襲討伐に同行して活躍した、神八井耳命の後裔と称する健緒組命の逸話によって「火の国」は生まれた。
その後、律令制度の導入とともに「肥後国」は成立したと思われる。なので645年くらいだろうね。その65年後にやっと初代国司(肥後守)が肥後国にやってくる。
国府が置かれたのは、国府の託麻国府、益城国府(場所が不明)、二本木の飽田国府という話。
そこで地方行政の長として、肥後守・肥後介・掾(じょう)・目(さかん)などの官職についた人々が支配者となってゆく。
そんなわけで、歴代国司を紹介してゆこう。
肥後の国司 四等官職
守と介の役割の違いはわからないけど、守が上位だと思う。
| 肥後守 | 肥後介 |
|---|---|
| 712年(和銅5年) – 718年(養老2年) | |
| 道君首名 生・天智天皇2年(633年)〜養老2年4月15日(718年5月18日) 初代国司、熊本市内各地に彼の事績が遺る | |
| 806年(大同元年)1月28日 〜 | 809年(大同4年)1月23日 – 812年(弘仁3年)4月19日 |
| 高倉殿継 生没年不明・高麗朝臣から高倉朝臣となる渡来人系官僚。 送高麗使として外交(渤海国など)に携わったり、中央・地方の官僚として 肥後国司としての事績は不明。 | 豊宗広人(とよむね の ひろひと) 生没年不明・堅部使主から豊宗宿祢に改姓した人。平安初期なのでいろいろ大変だったと思うのね。肥後での実績などは不明。 |
| 812年(弘仁3年)1月12日 -9月27日 | 812年(弘仁3年)4月19日 – |
| 大枝永山 生没年不明 着任してすぐに、刑部大輔に就くのだがすぐに肥後守として再任されている。事績は不明。 | 菅原清人 生没年不明 大枝永山の副官という立場か? |
| 812年(弘仁3年) 9月27日 | |
| 紀咋麻呂 (きのくいまろ) 生・ 天平勝宝7歳(755年)〜没・天長10年1月19日(833年2月12日) 肥後守はほんとに一瞬しかいなかったみたい | |
| 813年(弘仁4年)2月21日 – | |
| 大枝永山 再登場 | |
| 827年(天長4年)3月9日 – | |
| 藤原村田 生没年不明 藤原南家の巨勢麻呂の流れ。右少弁から肥後守に就任。その後、時期不明ながら蔵人・讃岐守などを歴任した。 | |
| 834年(承和元年)頃 | |
| 粟田 飽田麻呂 (あわた の あきたまろ) 宝亀8年(777年)か延暦23年(804年)に遣唐使に随行する留学生として唐に渡る。きっと優秀な人材だったのだろう。 諸陵寮という陵墓の管理だったり皇族葬儀の儀礼などを職掌としていた官僚となり、豊後介を兼任。そして、肥後守となる。このときは過去の経験を活かして、新羅などとの外交にも携わっていたかもしれない。 | |
| 836年(承和3年)以前 | |
| 藤原高総 詳細不明 | |
| 842年(承和9年)頃)従五位下 | |
| 橘真直(たちばな の まなお) 生没: 弘仁7年(816年)〜 仁寿2年6月20日(852年7月10日) 右大臣の三男。地方官も中央官僚も経験している。 | |
| 843年(承和9年)8月11日 – | |
| 菅原梶吉 生没年不明:詳細不明 | |
| 846年(承和13年)1月13日 – 847年(承和14年)2月11日 | |
| 大和 吉直 (やまと の よしなお) 肥後守として1年務めると兵部少輔などを歴任、仁明天皇の皇女の喪事を監護した。後に木工頭となり、天安への改元を諸天皇陵報告し、越前介、武蔵権介、常陸権介、安芸守などの地方官も務めた。また、従五位上に叙せられている。生没年は不詳。 | |
| 848年(嘉祥2年)1月13日 – 2月27日 | |
| 山池作(やまのいけつくり) 生没年不詳:直から宿禰に改姓したりしてい。る | |
| 848年(嘉祥2年)2月27日 – | |
| 高丘貞雄 | |
| 849年(嘉祥2年)1月13日 – 2月27日 | |
| 藤原 正世 (ふじわら の まさよ) 生没年不明。842年に従五位下・刑部少輔に叙任されたが、同年の承和の変に連座し、安芸権介に左遷された。恩赦により入京を許され、848年に治部少輔に任命された。849年には肥後守に転じ、以降は河内権守、河内守、常陸介と地方官を務めた。860年には大蔵少輔として京官に復帰したが、翌年再び地方官の因幡介に転じた。 | |
| 849年(嘉祥2年)2月27日 – | |
| 有雄王のちの清原 有雄(きよはら の ありお) 生年不明〜天安元年12月25日(858年1月13日) 舎人親王の玄孫で皇族の一人だったお方。彼は地方官として摂津守に任命された後、出雲守や肥後守を歴任し、嘉祥2年に従四位下、嘉祥3年には臣籍降下して清原真人姓を与えられ854年から清原有雄として肥後守を務める。彼は天安元年に散位従四位上で死去し、彼の死に対する人々の哀悼は極めて深かった。彼は人柄に風格があり、政治の理論にも熟練していた。 | |
| 853年(仁寿3年)8月8日 – | |
| (権介)県犬養氏河 | |
| 854年(斉衡元年)5月11日 – | |
| 橘仲宗 | |
| 855年(斉衡2年)1月15日 – 855年(斉衡2年)8月23日 | 855年(斉衡2年)1月15日 – |
| 高階 峯緒 (たかしな の みねお) 生没年不詳。平安時代初期から前期にかけての貴族で、左大臣・長屋王の玄孫である。彼は地方官を歴任し、従五位上から順調に昇進していき、斉衡4年に左中弁に転じた後、京官として大蔵権大輔・大蔵大輔を務め、貞観2年には従四位下に昇叙された。貞観3年には丹波守に転任し、再び地方官を歴任した後、貞観10年に従四位上に叙せられ、同年2月に神祇伯に任命された。 | 大原真室 |
| 855年(斉衡2年)8月23日 – 859年(貞観元年)12月21日 | |
| 藤原冬緒 (ふじわらのふゆお:生・大同3年(808年)〜没・寛平2年5月23日) 藤原京家、参議藤原浜成の孫であった。彼は官位を正三位、大納言に昇進するまでに能吏として清和・陽成朝を支え、政治的には振るわなかった藤原京家においては際立った存在であった。彼は儒学の才能に加えて、民政にも明るく、官田の設置を提唱して財政再建を行った。彼は公卿になる前に60歳を過ぎ、80歳を超える長命を保った。結果的に京家出身の最後の公卿となった。彼は、勘解由判官、式部少/大丞、六位蔵人、右少弁、伊勢介、春宮亮、肥後守、正五位下・右中弁、従四位下、従四位上、右大弁、参議、大宰大弐、弾正大弼、勘解由長官などの役職を歴任しており、彼の器量や見識は吏幹と称されていた。彼は、貞観11年(869年)12月に参議に任命され、公卿に列した。同時に大宰大弐に再任され、新羅の入寇で動揺する大宰府へ下向することになった。彼は、新羅の来襲への対策を踏まえて烽燧(敵の来襲を知らせる狼煙)について提言し、認められた。 | |
| 858年(天安2年)2月5日 – | 858年(天安元年)1月16日 – |
| 紀有常(きのありつね) 権守を務める。 紀有常は彼は幼少期から仁明天皇に仕え、後に左兵衛大尉として天皇に奉仕しました。その後、蔵人兼左近衛将監に任命され、文徳朝では右兵衛佐や右近衛少将といった役職を務めました。しかし、文徳朝末には地方官に転任することになり、清和朝では刑部権大輔や下野権守、信濃権守といった地方官を務めました。最終的には従四位下行周防権守の地位に昇進しましたが、貞観19年に亡くなりました。彼の享年は63歳でした。 有常は、清らかでつつましく、礼儀正しい性格の持ち主であり、勅撰歌人として『古今和歌集』『新古今和歌集』にそれぞれ1首ずつ採録されている。彼は『伊勢物語』16段で、妻が尼になって去ってしまったことを悲しんだが、友人と和歌のやりとりをした。 生誕 弘仁6年(815年) 死没 貞観19年1月23日(877年2月9日) | 藤原正峯 |
| 859年(貞観元年)1月13日 – | |
| 権介)大原真室 | |
| 864年(貞観6年)1月16日 – | |
| 橘朝雄 | |
| 860年(貞観8年)11月29日 – | |
| 小野貞樹(おの の さだき) 藤原不比等没後に、藤原四兄弟の陰謀で無念の死を遂げた「長屋王」の子孫だという説もあるが、定かではない。一般的に長屋王の子孫は高階を名乗っているので、実に怪しい。 肥後守以外に甲斐守など地方官を歴任しているがその治績は不明。古今和歌集の勅選歌人として名を遺している。小野小町と贈答歌がちょっと生々しい。 生没年不明 | |
| 860年(貞観2年)11月27日 – 864年(貞観6年) | |
| 藤原 真数(ふじわら の まかず) 藤原北家の人。wikiなどの説明を見ると、中央官僚から、地方官僚として左遷されたようだ。最終的には、刑部大輔として京官に復している。 生没年不明 | |
| 865年(貞観7年)1月27日 – 866年(貞観8年)9月22日 | |
| 紀 夏井(き の なつい) 大納言・紀古佐美の曾孫。美濃守・紀善峯の三男。官位は従五位上・右中弁。熊本での詳細は不明だが、領民に慕われていたらしい。興味深いので別項に記す。 生没年不詳。 | |
| 866年(貞観8年)11月29日 – | 866年(貞観8年)1月13日 – |
| 在原 安貞(ありわら の やすさだ) 平城天皇の孫で高岳親王の息子。wikiによると任期がアヤシイ。在原業平の従兄弟だったみたい。薬子の変で臣籍降下した人。いろいろ苦労した人らしいが、肥後守としての事績は不明。 生没年不詳 | 平住世 |
| 869年(貞観11年)1月13日 – | |
| 橘子善 | |
| 877年(元慶元年)頃 | |
| 藤原智泉 | |
| 879年(元慶3年)8月17日 – 880年(元慶4年)1月 | |
| 藤原 山蔭(ふじわら の やまかげ) 権守として。wikiの肥後守の項目には記載があるが、彼の項目にはこの時期に参議となっている。一方で、茨木市(大阪府)の資料には、このときに、肥後権守(任)・右大弁(兼)と書かれている。いずれにしても在任期間は1年なので、熊本には来てないんじゃないかな。 四条流包丁式という、日本料理の始祖で、料理の神様になっている人っぽい。 生誕 天長元年(824年) 死没 仁和4年2月4日(888年3月20日) | |
| 880年(元慶4年)5月13日 – | |
| 藤原 房雄(ふじわら の ふさお) 藤原南家の人。若干乱暴者だったので、肥後は大国ではあるけど左遷だったみたい。 生誕 不明 死没 寛平7年5月18日(895年6月14日) | |
| 881年(元慶5年)2月15日 – 882年(元慶6年)2月15日 | |
| 源 直(みなもと の すなお) 嵯峨源氏、左大臣・源常の三男。 生誕 天長7年(830年) 死没 昌泰2年12月26日(900年1月30日) | |
| 885年(仁和元年)1月16日 – | |
| 藤原 時長(ふじわら の ときなが) 元慶3年(879年)斎宮・識子内親王の行禊に際して後次第司長官を務めたという記録があって、肥後守になったものの実際に熊本には来ず。一度、位階を落とされたらしい。 なので同時に権守が立てられる。大国という扱いだが、辺境の土地だったのかなぁ。 生没年不明 | |
| 885年(仁和元年)2月20日 – 886年(仁和2年)1月16日 | |
| 藤原 有実(ふじわら の ありさね) 赴任してこなかった時長の代わりに権守として着任したっぽい。最終的に参議(正三位)まで出世する人。1年の任期で何をしたのかな。 生没年不詳 | |
| 886年(仁和2年)1月16日 – | 886年(仁和2年)1月16日 – 2月21日 |
| 藤原 門宗(ふじわら の かどむね) 有実のあとに権守となる。 中央官僚として出世して、従四位まで。地方官としては肥後権守と近江守を経験。 生没年不詳 | 大神良臣 |
| 886年(仁和2年)6月19日 – | |
| 藤原 是行(ふじわら の これゆき/これつら) 権守が2代続いた後、時長の後任として着任。地方官を歴任した人。 従四位下にまで昇進する。 生没年不詳 | |
| 891年(寛平3年)1月30日 – 893年(寛平5年)1月11日 | |
| 三善清行 | |
| 893年(寛平5年)3月15日 – | |
| 平 惟範(たいら の これのり) 桓武平氏で中納言・従三位まで昇進する。この頃の朝廷は臣籍降下して源氏となっていた皇子が宇多天皇として即位している。やはり天皇と藤原氏の権力闘争というか、そういうややこしい時期が続いていたのかな。 生誕 斉衡2年(855年) 死没 延喜9年9月18日(909年11月3日) | |
| 909年(延喜9年)1月 – | |
| 多治是則:詳細不明 | |
| 925年(延長3年)頃 | |
| 藤原令門 | |
| 926年(延長4年)頃 | |
| 藤原行直:詳細不明 | |
| 943年(天慶6年)3月7日 – | |
| 藤原時佐:詳細不明 | |
| 947年(天暦元年)頃 | |
| 藤原 佐忠(ふじわら の すけただ) 権守として。歌人としても有名。 | |
| 961頃 | |
| 紀 師信 | |
| 978年(天元元年)秋 | |
| 権介:藤原遠美 | |
| 978年(天元元年)秋 – | |
| 権介:藤原頼兼 | |
| 986年(寛和2年) – 990年(正暦元年)6月 | |
| 清原 元輔(きよはら の もとすけ) 清少納言のパパンとして有名。というか父親だけあって文才もあり、歌人としても有名。 79歳という老境でで肥後守の任を受けたのは、清原家の経済基盤が盤石ではなかったからだとも言われている。北岡神社の飛地境内に清原神社があるよ。 生誕 延喜8年(908年) 死没 永祚2年(990年)6月) | |
| 990年(正暦元年)8月30日 – | |
| 源為親 詳細不明 | |
| 1005年(寛弘2年) | |
| 藤原 保昌(ふじわら の やすまさ) 藤原南家巨勢麻呂流の貴族でありながら、武人として有名。実際に坂上田村麻呂・藤原利仁・源頼光とならび、伝説的な武人4人の一人だったり、源頼信・平維衡・平致頼らとともに道長四天王として有名。肥後守としての事績は北岡神社を勧請したことだろうか。 生誕 天徳2年(958年) 死没 長元9年(1036年)9月) | |
| 1010年(寛弘7年)頃 | |
| 大江忠孝 詳細不明 | |
| 1023年(治安3年) – 1027年(万寿4年)頃 | |
| 藤原致光 詳細不明 | |
| 1028年(長元元年) – | |
| 高階 成章(たかしな の なりあき) 中央の官僚としても活躍しておいたみたいで、肥後守や太宰大弐として、九州の地方を統括する役目も負っていた。肥後には常駐しなかったと想像している。 生誕 永祚2年(990年) 死没 天喜6年2月16日(1058年3月13日) | |
| 長元・長暦頃? | |
| 藤原 定任(ふじわら の さだとう) 詳細不明 | |
| 1053年(永承3年)頃 | |
| 高階章行 詳細不明 | |
| 延久頃 | |
| 藤原義綱 詳細不明 | |
| 承暦頃 | |
| 源時綱 詳細不明 | |
| 1091年(寛治5年) | |
| 中原 師平(なかはら の もろひら) 肥後守従四位下として、70歳で亡くなる。 生年:治安2年11月28日(1022年12月24日) 没年:寛治5年9月17日(1091年10月31日 | |
| 1092年(寛治6年) – | |
| 藤原 盛房(ふじわら の もりふさ) 歌人として知られている。 | |
| 1097年(承徳元年) – | |
| 高階基実 詳細不明 | |
| 1102年(康和4年) – 1106年(嘉承元年) | |
| 藤原為宣 詳細不明 | |
| 永久頃 | |
| 藤原忠兼 詳細不明 | |
| ーーー | |
| 高階清泰 詳細不明 | |
| 1127年(大治2年) | |
| 藤原公章 詳細不明 | |
| 1128年(大治3年) | |
| 高階泰重 詳細不明 | |
| 1137年(保延3年) – | |
| 平清盛(たいら の きよもり) 超有名人。肥後守という官職もあったけど、熊本に来たことはなかったろうね。代官的な人が管理してたのかな。 | |
| 1142年(康治元年) | |
| 清原信俊 詳細不明 | |
| 1144年(天養元年) – 1154年(久寿元年) | |
| 源国能(俊国) 詳細不明 | |
| 1150年(久安6年) | 時期不明 |
| 石浦経国 | |
| 時期不明 | |
| 平 貞能(たいら の さだよし) 世の中は武家の時代となっている。平家の台頭。この人は平清盛の腹心として有名。肥後守としての実績は不明ながら、九州での活躍が顕著。 生没年不明 | 源家基 |
| 時期不明 | |
| 源 頼成(みなもと の よりなり) 大和源氏。藤原道長次代の人 生没年不詳 | |
| 南朝1 | |
| 菊池 武重(きくち たけしげ) 地元の豪族が肥後守になった最初期の事例かと。北朝方は「守護」を置くようになっているので、肥後守は南朝方が最後といえる。建武の新政による恩賞として肥後守になった。お手柄は父や兄の働きなんだけどね。 菊池氏 | |
| 南朝2 | |
| 菊池 武士(きくち たけひと) 武重の弟だが、庶兄の武光に追放されてしまう。 菊池氏 | |
| 南朝3 | |
| 菊池 武光(きくち たけみつ) 北朝とのバトルで活躍し、懐良親王を征西大将軍としてお迎えしたりして、菊池一族のピークを作る。 菊池氏 | |
| 南朝4 | |
| 菊池 武政(きくち たけまさ) 武光の息子。父の跡をついで半年で世を去る。 こういう不幸が菊池氏の衰亡を早めたんだろうね。 菊池氏 | |
| 南朝5 | |
| 菊池 武朝(きくち たけとも) 北朝と合一する中で、肥後の守護代となる。この後の肥後守は武家の官位として流通するくらいで、支配者としての意味合いがなくなるけど、菊池一族は滅亡まで肥後守を名乗っていたそうだ。 菊池氏 |