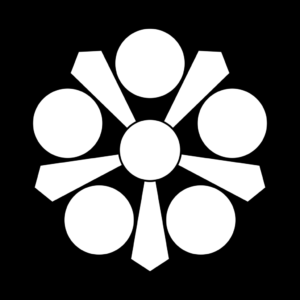手永(てなが)とは、江戸時代に肥後藩(現在の熊本県)で採用されていた地方行政制度。
領内を数ヶ村〜数十ヶ村程度にまとめた行政区画。大庄屋あるいは惣庄屋と呼ばれる責任者が置かれた。
手永制度の起源は、細川氏が豊前小倉藩主であった時代にまで遡り、慶長年間(1596-1615)頃、領内の統治を効率化するために導入されたと考えられる。その後、細川氏が肥後熊本藩に移封(寛永9-1632年)されると、寛永年間(1624-1644)頃に手永制度も肥後藩に導入された。
当初は100以上の手永が存在したが、統廃合を繰り返し、承応2年(1653年)には59。200年後には51まで減っている。
もしかしたら、平成の大合併みたいな感じだったのかな?
手永の概要
- 村をまとめて統治: 手永は数ヶ村〜数十ヶ村程度で構成されており、惣庄屋と呼ばれる責任者が置かれた。惣庄屋は、年貢の徴収、治安の維持、訴訟の裁定など、村に関する様々な事務を担当。
- 自治的な運営: 手永は、藩からある程度の自治権を与えられており。惣庄屋は、村人たちと協議しながら、手永内の様々な問題を解決。会所 と呼ばれる役所が設置され、惣庄屋を補佐していた。
- 兵農一致: 手永は、軍事組織としての役割も担っていました。惣庄屋は、農民を兵士として編成し、領内の防衛に当たる。
手永制度は、肥後藩の統治に大きく貢献する。惣庄屋を中心とした自治的な運営により、領内の秩序が維持されるとともに、農民の負担軽減にもつながったと思われる。また、兵農一致の体制は、肥後藩の軍事力を強化する役割を果たした。
明治時代に入り、中央集権体制が確立されると、手永制度は廃止されたが、手永制度で培われた自治的な精神は、その後も肥後の人々の気質に受け継がれていると言われる。
惣庄屋 について
他藩では大庄屋と呼ばれる存在。郡代(手永より広い範囲の首長)の配下という扱いになる。
もともとは旧菊池・阿蘇氏の家臣が世襲で請け負うなどの武士的な存在であったが、時代を下ると実力のあるものが任命されるようになったという。
有名な惣庄屋さん
肥後の手永制度においては、地域社会の発展に大きく貢献した著名な惣庄屋が数多く存在します。
| 氏名 | 手永名 | 活動時期 | 主な功績 |
|---|---|---|---|
| 布田保之助 | 矢部手永 | 江戸時代後期 | 通潤橋の建設 |
| 中山手永 | 美里町 | 1845年頃 | 岩野用水の建設 |
| 深水三河入道 | 求麻郡 | 1587年 | 秀吉より領地を拝領、地域に影響力を持つ |
| 小代伊勢守親忠 | 不明 | 江戸時代初期 | 加藤清正より知行を与えられる |
| 松井氏 | 八代手永 | 江戸時代 | 八代城代として八代を手永として支配 |
| 河野太郎助 | 南関手永 | 1813年頃 | 婚礼葬礼の奢侈を取り締まる |
| 遠山弥二兵衛 | 中村手永 | 1856年頃 | 農作物の仕法を調査、村組を組織 |
| 横田氏/田上氏 | 甲佐手永 | 寛永~宝暦年間 | 甲佐手永の惣庄屋を務める |
| 馬場三郎兵衛 | 小国郷(後に馬場手永) | 1714年頃 | 小国郷の惣庄屋に任じられ、手永名となる |
| 鹿子木量平 | 益城郡杉嶋手永や野津手永、高田手永 | 江戸時代後期 | 八代海沿岸の干拓事業 |
矢部手永の惣庄屋であった布田保之助は、用水路として有名な通潤橋の建設を主導しました 。この巨大な石造りの水路橋は、地域の農業発展に大きく貢献し、彼の功績は現在でも高く評価されています。また、美里町にある岩野用水は、江戸末期の1845年(弘化2年)に中山手永によって建設されました 。これもまた、惣庄屋が中心となって地域の灌漑事業を推進した好例と言えるでしょう。
天正15年(1587年)に豊臣秀吉から肥後国求麻郡内で領地を与えられた深水宗方(深水三河入道)は、旧勢力としてその存在を認められており、地域に大きな影響力を持っていました 。加藤清正に肥後国領知方目録が与えられた際、3000石の知行を与えられた小代伊勢守親忠は、国侍に知行を分け与えており、初期の肥後における有力者の一人であったと考えられます 。八代城代として代々置かれた松井氏は、八代を手永として支配し、その地域における惣庄屋としての役割も果たしました 。
文化10年(1813年)頃の玉名郡南関手永の惣庄屋であった河野太郎助は、婚礼葬礼の奢侈を取り締まる布達を庄屋に伝え、村々の組合運営に関わりました 。安政3年(1856年)の山鹿郡中村手永の惣庄屋であった遠山弥二兵衛(遠山神社)は、村々に諸作物の仕法を調査報告させ、久原組と呼ばれる村組を組織しました 。寛永年間から宝暦年間にかけて甲佐手永の惣庄屋を務めた横田氏(後に田上と改姓)は、横田手永が廃止された後も甲佐手永で重要な役割を果たしました 。正徳4年(1714年)頃に小国郷の惣庄屋に任じられた馬場三郎兵衛は、その功績により、小国郷が馬場手永と改称されるほどの影響力を持っていました 。
これらの事例から、惣庄屋は単なる行政官としてだけでなく、地域社会のリーダーとして、インフラ整備から社会秩序の維持、経済発展まで、多岐にわたる分野で重要な役割を果たしていたことがわかります。
肥後の手永一覧
熊本県庁の資料には、寛永年間から宝暦年間にかけての肥後全藩の手永の変遷と、各郡の手永名が記載されています 。以下に、主な手永名を郡別に列挙します。
飽田郡:銭塘、権藤、横手、京町、五町、池田
託麻郡:田井島、本庄
上益城郡:中島、矢部、木倉、横田、豊田、沼山津、鯰
下益城郡:河江、廻江、赤見、杉島
宇土郡:正院、久木野
八代郡:水俣、津奈木、湯浦、佐敷、市瀬、大野、二見、田浦、種山、高田、興善寺、野津、郡浦、松山、中山、砥用
葦北郡:高田、二見、田浦、種山、興善寺、市瀬、大野、久木野、佐敷、湯浦、津奈木、水俣
菊池郡:深川、隈府
阿蘇郡(合志郡):坂梨、内牧、野尻、菅尾、高森、鳥子、大津、板井、竹迫、河原、西寺
玉名郡:高瀬、湯町、南関、志柿、府本、荒尾、中富、坂下、小永、内田、伊倉
山鹿郡:山鹿、中村
天草方面は天領だったし、人吉球磨方面は相良氏の所領だったので、
これらの手永は、時代によって統廃合や名称変更が行われたことが記録されています 。球磨郡は相良藩領であったため、この一覧には含まれていません 。このように、肥後藩は細かく分割された手永によって、藩全体の統治を行っていたことがわかります。
参考サイト
- 手永,Wikipedia
- 手永制度が育んだ肥後人気質,ミツカン 水の文化センター
- 第三章近世の地方制度(PDF),熊本県
- 具体的にどんな資料の「第三章」なのかは不明