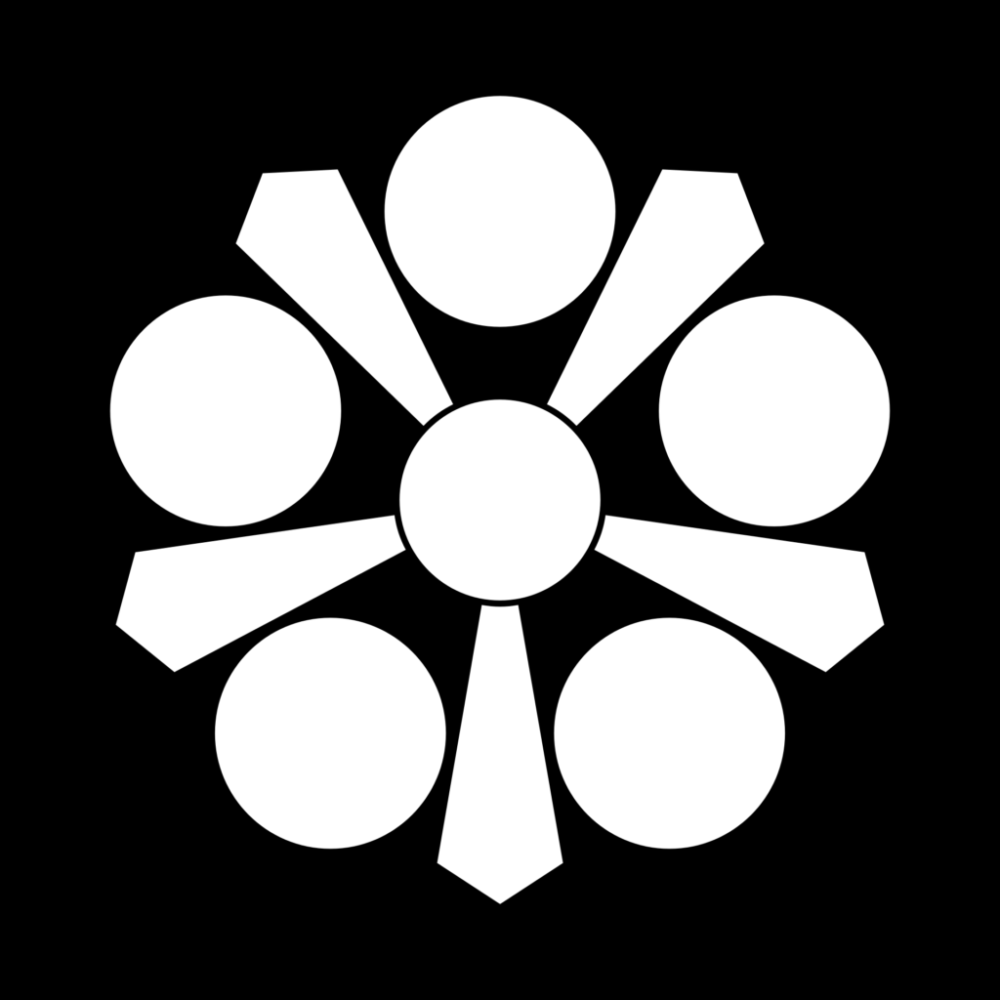
相良氏は藤原南家工藤氏の流れをくむ武家で、鎌倉時代に遠江国相良荘(静岡県)から肥後国球磨郡(熊本県)へ移住しました。相良周頼が苗字の起源とされますが、子がなく伊東氏から養子を迎えたため、日向伊東氏とも近縁関係にあります。
鎌倉時代、相良頼景は多良木荘に下向し、鎌倉幕府に仕えました。建久9年(1198年)、相良長頼が人吉荘の地頭となり、以後700年以上にわたり同地を治めました。承久3年(1221年)の承久の乱では長頼が功績を挙げ、家紋「梅」の由来となりました。
南北朝期には一族が南朝・北朝に分かれ対立しましたが、室町時代には球磨郡を統一し、戦国時代には相良義滋が戦国大名として台頭しました。江戸時代には人吉藩主として存続し、明治維新後は華族に列せられました。相良氏の統治は地域文化の保護と寛容な政策で知られ、700年以上にわたり球磨地域で影響力を持ち続けました。
相良氏は戦国時代、江戸時代を通じて人吉を支配し続けた稀有な大名家で、島津氏や大友氏などの圧力を受けながらも存続しました。豊臣秀吉の九州征伐や関ヶ原の戦いでも重要な役割を果たし、徳川幕藩体制下で大名として存続しました。明治維新後は華族となり、現在もその文化遺産が人吉球磨地域に深く根付いています。
そんな相良氏の歴代当主を紹介します。
相良氏の歴代当主
- 相良長頼
- 相良長頼は治承元年(1177年)に遠江国相良荘で生まれ、父頼景が肥後国多良木荘に下向した後も相良荘に留まりました。建久9年(1198年)、源頼朝の命で人吉荘に下向し、矢瀬氏を討ち人吉城を奪取。その功績で元久2年(1205年)に地頭職を得ました。承久3年(1221年)の承久の乱では北条時房に従い、宇治川の戦いで活躍。旧領相良荘の回復と播磨国飾磨郡の新恩を受け、相良家の基盤を築きました。建長6年(1254年)、78歳で没し、法号は蓮佛です。
- 相良頼親
- 相良頼親は鎌倉時代の武将で、相良長頼の長男です。6歳で元服し「四郎兵衛尉頼親」と名乗り、幼少期には将軍源実朝の鶴岡八幡若宮参拝に同行する栄誉を受けました。承久元年(1219年)、実朝暗殺を機に剃髪し「観仙大徳」と改名、後深草天皇から禅師号を賜りました。父長頼の留守中は人吉で内政を担当し、宝治元年(1247年)には井口八幡神社を創建。建長6年(1254年)、家督を継ぎましたが翌年弟の頼俊に譲り隠棲。文永元年(1264年)、68歳で逝去しました。息子頼明は永留氏を称し、後に宗家を継ぐ長続が出たとされていますが、その系譜には不明点も残ります。
- 相良頼俊(長頼の三男、兄の頼親より家督を譲り受ける)
- 相良長氏
- 相良頼広
- 相良定頼
- 相良前頼
- 相良実長
- 相良前続
- 相良堯頼
- 相良長続(永留氏8代・実重の子。堯頼を逐い多良木兄弟を討滅する)
- 相良為続
- 相良長毎
- 相良長祗
- 相良長定(長続の孫。正統なる嫡流を主張し、長祗を逐い政権を奪取する)
- 相良義滋(長祗の兄。長定を逐う)
- 相良晴広(上村頼興の子で、義滋の養嗣子)
- 相良義陽(晴広の子)
- 相良忠房(義陽の長男)
- 相良頼房(義陽の次男。初代人吉藩主)
- 相良頼寛
- 相良頼喬
- 相良頼福
- 相良長興
- 相良長在
- 相良頼峯
- 相良頼央
- 相良晃長(高鍋藩秋月氏からの養子)
- 相良頼完(羽林家鷲尾家からの養子)
- 相良福将(苗木藩遠山氏からの養子)
- 相良長寛(岡山藩池田氏からの養子)
- 相良頼徳
- 相良頼之
- 相良長福
- 相良頼基
- 相良頼紹
- 相良頼綱
- 相良頼知
- 相良知重
この一覧は鎌倉時代から明治維新まで続く歴代当主を網羅しています。


