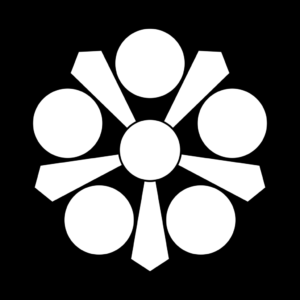武田流騎射流鏑馬
武田流騎射流鏑馬 は、熊本県重要無形文化財で武田流流鏑馬保存会のみなさん幽玄の伝統を受け継いでおられます。
流鏑馬とは
流鏑馬 はいわゆる三つ物のひとつで、流鏑馬以外には戦勝祈願として懸けた笠を射る笠懸、犬を追って射る犬追物のが知られています。
流鏑馬は「天下泰平・万民息災・五穀豊穣」を祈願して三つの的を射るものを指します。
また、騎射とは場上で弓を射るもので、弓の道には地上で射る 歩射があります。
中でも流鏑馬は騎射の代表であり、平安時代には朝廷で公家の儀式として、鎌倉時代以降は武士の武技の修練として盛んでした。
今日、流鏑馬は豊穣祈願の祭礼として各地に残っていますが、時の流れとともに本来の形を失ったものが多いようです。
武道としての流鏑馬は、源氏の流れを汲む肥後の武田流(細川家)と小笠原流(徳川家)によってその正伝が護持されています。
武田流流鏑馬とは?1100年の歴史を持つ伝統武芸
武田流流鏑馬は、平安時代初期に起源を持つ、1100年の歴史を持つ伝統武芸です。清和天皇の皇子から源氏七代に伝わり、武田家と小笠原家に分かれました。武田流は、若狭武田家から細川藤孝(幽斎)を経て、家臣の竹原惟成に伝承されました。
竹原家による継承
細川忠興・忠利が肥後に入国してからは、竹原家が宗家師範として武田流を継承。藩校の時習館では、二条流和歌式や礼法とともに武田流流鏑馬が学ばれていました。昭和9年以降は、熊本藩主細川家を祀る出水神社で奉納されています。
演技の種類
- 天長地久式: 平和と人馬の健康、豊かな実りを祈願する儀式
- 流鏑馬式: 疾走する馬上から的を射る
- 木馬体配: 木馬を用いて流鏑馬の基本や技術を習得する練習
礼法
武田流には、相手への尊敬や心遣いを形にする美しい礼法も伝わっています。細川流礼法として、武田流騎射流鏑馬とともに竹原家が継承してきました。
現在の武田流
竹原陽次郎氏が設立した保存会によって、武田流流鏑馬は現在も継承されています。竹原陽次郎氏の逝去後は、竹原浩太氏が宗家師範を継承しています。
関連情報
- オールクマモト:武田流と小笠原流の合同流鏑馬奉納を見た(出水神社)
- オールクマモト:水前寺成趣園・出水神社(熊本市)
参照元
- 武田流騎射流鏑馬保存会:武田流について
※実施内容が予告なく変更となる場合がございます。公式サイトにて最新情報をご確認ください。